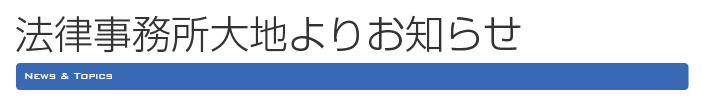【代表弁護士から】館山市
2016年06月01日(水曜日)
先日、館山市を訪れました。
千葉市も館山市も同じ千葉県ですが、かなり距離があります。
調べてみたら、千葉市~館山市間は90キロ以上。これを東京から東海道に引き直すとどこまで行くか・・・といいますと、小田原まで行ってしまいます!
小田原というと、神奈川県の西方でです。
遠いはずです。
東京~小田原間は新幹線なら30分程度。
もちろん千葉から館山に新幹線はありません(千葉県内に新幹線はありませんからね)。最近は特急の本数も減らされてしまってますので、公共交通機関ではますます行きにくくなっています。高速道路が館山市の近くまで伸びましたから、JRよりは高速バスの方が便利なのかもしれませんね。
館山市。とっても良いところです。
坂東三十三観音巡りというのがありまして、これは四国八十八ヶ所とかそういうのに似ているのですが、関東地方全域に散らばっているので、かなり回りにくい。その三十三箇所目、結願の寺院が館山市の那古寺です。
坂東三十三観音の寺というのは、小高い丘や山の上にあるところが多いんですが、ここも例外ではないです。
海がよく見えます。
鏡ヶ浦という綺麗な名前の湾です。
観音様にお参りして、目を移せば浄土にも似た穏やかな海があって・・・という感じだったのかなあと古きを偲ぶのもまた一興です。
【スタッフ雑談】県の石
2016年05月27日(金曜日)
「県の石」というのが5月10日の地質の日に発表されました。
日本地質学会が大地の性質や成り立ちに関心をもってもらおうと、全国47都道府県において特徴的に産出あるいは発見された岩石・鉱物・化石を、それぞれ「県の石」として選定したものだそうです。
千葉県の石の岩石部門で選ばれたのは、先月話題にした「房州石」。
鉱物は「千葉石」(「ちばせき」と読みます)で、千葉県において世界で初めて発見された新鉱物。
化石は「木下貝層の貝化石群」。木下貝層は12万年前に関東平野一円が「古東京湾」と呼ばれる内湾の浅い海だったころに堆積した地層で、当時生息していた貝類等の化石が密集して産出するのが特徴。印西市の木下万葉公園内の露頭は古生物、地質、堆積学の研究も数多く、学術的にも重要とのことで、平成14年に国の天然記念物に指定されています。貝化石は100種類以上が報告されているそうです。
日本地質学会のホームページには各県の石が写真とともに紹介されており、千葉ではみることのできない岩石や化石もあり興味深いです。
(R)
【代表弁護士から】「弁護士経済危機」(?)
2016年05月20日(金曜日)
弁護士というと、儲かる商売の典型のようにいわれておりましたが、最近では弁護士数が増えてきたこともあり、収入が減少している弁護士も増えてきております。
千葉県弁護士会では、これを「弁護士の経済危機」としており、平成27年度の会務方針として、弁護士の収入の激減に対処するための対応というものを行いました。
とこう書きますと、収入が減少している弁護士のために、弁護士会が仕事を取ってくるようなことをするのかと思われますが、そのようなものではく、
1 組織が縦割りになっているから、横断的な組織(「弁護士業務整備・拡充対策本部」)を立ち上げる
2 収入源の根本原因となっているのは、司法試験の合格者の数だから、これを制限するように求める
というものでした。
目標は弁護士の収入増という、収入が減っている弁護士は大喜びしそうなものなのですが、実際の政策は、組織を新たに作ることだったり、司法試験の合格者数という国の政策で決められるものに対して要請するというもんだったりして、竜頭蛇尾という感が拭えません。
弁護士の収入が減少しているというのであれば、高い会費(千葉県弁護士会の会費は月額で3万円)を引き下げれば良さそうなものですが、そのようなことには一切触れられていません。
弁護士というと、唯我独尊タイプ、自由な発想をするタイプのように思われるかもしれませんが、弁護士会という全会員が加入しなければならないような組織ともなると、硬直的な、かつ組織の論理を優先したものになりがちであることは、他のどこかの組織とも変わることがないようです。
【スタッフ雑談】新緑が美しい香取神宮にて
2016年05月16日(月曜日)
先日、香取神宮(千葉県香取市)で春季弓道大会が行われました。
今回は大会運営のお手伝いをするために、友人と参加してきました。実に22年ぶりに弓道大会を見たのですが、私が当時現役で弓を引いていた時とはだいぶ雰囲気が変わり、とても新鮮でした。
弓道は、的に当たった矢の本数で勝敗を競うのですが、今回の大会では、最初に2本、その後、4本放ち、計6本中何本的に当たったかで勝敗を決めるルールでした。同率本数の場合、順位決めは競射(1つの的に同率順位者が1本ずつ矢を放ち、的の中心により近い矢から順位が決まるもの)で行われました。競射はとてもスリリングです。的の中心を狙って矢が次々に放たれ、的に突き刺さる様は圧巻で芸術的でした。
一般の部の優勝者と学生の部の優勝者の2名で、最後は総合優勝を決めるための決勝戦を行ったのですが、この決勝戦は射詰(いづめと読み、それぞれの的に向かって1本ずつ矢を放ち、どちらかが的を外すまで行い、的を先に外した方が負け)で行われました。そして、学生の部の優勝者である地元高校生が見事優勝を飾りました(残念ながら私の母校ではありませんでしたが)。
見ていると弓を引きたくなりました。今年の秋の大会にはエントリーできるよう精進したいと思っています。(S)
【代表弁護士から】千葉氏と佐倉
2016年05月06日(金曜日)
千葉市は今年「開府890年」ということで、千葉氏をアピールする戦略です。
ただ、千葉氏が千葉市中心部を拠点にしていたのは、それほど長い期間ではありません。
350年くらいではないでしょうか。
千葉市中心部が拠点だったのは1126年~文明年間(1469~1486年)くらいです。
文明年間以降は、本佐倉城に拠点を移しています。
本佐倉城は、佐倉市・酒々井町にまたがっている中世の城で、現在は城跡しか残っていません。
国の史跡で、学術的な価値は高く、酒々井町では地元の方によるボランティアガイドに力をいれています。
戦国時代に千葉氏は後北条氏の傘下となりますが、豊富秀吉によって後北条氏が滅ぼされると同時に滅亡。
江戸時代は、佐倉市中心部に城が築かれ、佐倉藩の支配下となりますので、千葉氏は江戸時代には歴史的な存在となってしまいました。
千葉市では、「千葉氏サミット」を8月21日(日)に開催するそうです。
千葉氏にゆかりのある自治体の方を招いて、シンポジウムや、各自治体の物産品の展示・販売などを行うとのことなのですが、詳細はまだ明らかになっていません。
ところで、明治時代になって、千葉市が県庁所在地となり、裁判所の本庁は千葉市に置かれるようになりました。
佐倉市までは千葉市から20キロ程度とそれほど離れてはいないのですが、佐倉市に裁判所の支部があるのは、佐倉藩が存在していたことと関係があるのでしょう。
佐倉支部の管轄は、四街道市や成田市に及びかなり広い範囲です(そのほかには八街市、印旛郡、印西市、白井市、富里市)。