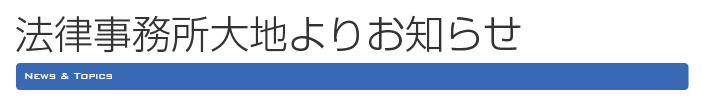【代表弁護士から】5月も下旬。伊能忠敬没後200周年行事。
2018年05月22日(火曜日)
5月ももう下旬です。
暑かったかと思うと、夜は寒かったりして体調を崩しやすい時期でもあります。
今年は伊能忠敬の没後200年に当たります。
伊能忠敬は今の九十九里町に生まれ、佐原(香取市)に養子に行き、家督を譲った後といいますから、今でいえば定年退職した後に江戸に出て測量等を学び、全国を回って測量をして、地図を作ったという熟年の星ともいえる人物です。
伊能忠敬が生まれて育った九十九里町や佐原は千葉県であり、千葉県の郷土の偉人でもあります。
先日香取市の方でシンポジウムがあったので、参加してきました。
伊能忠敬の子孫だけでなく、間宮林蔵の子孫(間宮林蔵は伊能忠敬から測量を学んでいました)、シーボルトの子孫(シーボルトは伊能図を国外に持ち出そうとして国外追放になりました)が勢揃い。
シーボルトの子孫は、あのツェッペリン号の子孫でもおり、ドイツの城住まい。そのような広大なスペースのおかげでシーボルトの大量のコレクションが保存が可能となったと聞いて、後世に伝えていくのはモノであれ、言葉であれ、どこかで誰かの努力と運が必要なのかなと思ったりしました。
さて、ブログの方は、民事訴訟の流れについて記事を書きました。
「弁護士さんに裁判を依頼しているのだが、何をやっているのかさっぱりわからない。」「ちゃんとした説明がない」「説明はされているがよくわからない」というご相談をいただくので、これは民事訴訟の流れ、大雑把な構図を弁護士が説明していないからではないかなと思いました。
弁護士に裁判を依頼しているのに、何をやっているのかわからない、わかりにくいというのでは、訴訟をしている意味が半減してしまいます。
流れを把握することが、目標達成のための一助になるかと思いますので、ご興味のある方は御覧ください。
→こちら
【スタッフ雑談】たんぽぽコーヒーと棚田
2018年05月14日(月曜日)
今年のゴールデンウィークもあっという間に終わりました。弓道大会なども入っていたので連日忙しかったのですが、空いた中日に思い立ち、友人とふらりと大山千枚田へ遊びに行ってきました。
快晴だったので、田植えがすでに完了した棚田は本当に美しかったです。苗が育つともっともっと美しいのだろうなぁと思います。風に揺れる稲を想像して、また夏に遊びに来ようと思いながら夢中で写真を撮りました。
大山千枚田の棚田を眺める場所から少し歩いたところに、カフェがあります。そこで初めて、たんぽぽコーヒーを飲みました。コーヒーといっても、コーヒー豆ではなく、原料はたんぽぽの根です。たんぽぽの根を焙煎したコーヒー色の飲み物なのですが、私は恥ずかしながら初めて知りました。これがまた美味しくてはまりそう。カフェでは茶葉は販売していませんでしたが、どこでも購入できるものらしいです。調べてポチッと(ネットショッピング)してみます。(S)
【代表弁護士から】ゴールデンウィークも終了。調停と判決について、それぞれ考えてみました。
2018年05月07日(月曜日)
ゴールデンウィークも終わりました。
連休明けはさすがに仕事の勘が取り戻しにくいですね。
これから徐々に体を慣らしていかないといけません。
さて、この間は調停と判決についてブログで記事を書きました。
最近は家事の調停が多いですね。
一番多いのは離婚調停とか遺産分割調停です。
調停といえば、かならず調停委員と対峙するわけですが、調停委員の仕事ぶりを見ていると司会者のようだなと思います。
司会というのはその場を仕切るわけですから優秀でなければ務まりません。
「調停は話し合い」とはよく言われますが、単に話しをしていけばまとまるというような世の中でもないし、調停外で話し合いをしてきたけれども当事者同士では話し合いがつかないというケースしか裁判所には来ないわけですから、そう簡単に話し合いがつくというものでもありません。
そんなことを考えてブログの記事にしてみました。
→こちら
調停でも話し合いがまとまらない、裁判(訴訟)になってそこでも話し合いがまとまらないということは、昔よりは増えてきている感じがします。
そうなると、判決になる。
民事事件や家事事件の判決を見ていると、以前よりだいぶコンパクトになったな、簡潔になったなと思います。原因はどこにあるんでしょうね。
裁判官が忙しくなったということはあるのかなと思います。
それと裁判官の中には、判決は短くてよいという方もいる。
以前最高裁の長官をやった矢口洪一さんはそう言っていますね。
そういう考え方が浸透してきたというのもあるのかもしれません。
ただ、それでは当事者は納得がいかないよという感想をもつことも多い。
弁護士ですら、この判決は納得がいかないと感じることも多いので、当事者の方はなおさらだと思います。
そんなことを書いてみました。
→こちら
【代表弁護士から】大型連休中の事務所の執務日時について
2018年04月27日(金曜日)
大型連休中の事務所の執務日時は以下のとおりです。
4月28日~30日 休み
5月1日、2日 通常どおり
5月3日~6日 休み
5月7日~ 通常どおり
以上となりますので、よろしくお願い致します。
【スタッフ雑談】美しき小さな雑草の花図鑑
2018年04月27日(金曜日)
素敵な図鑑が出たよと友人が教えてくれたのが、「美しき小さな雑草の花図鑑」(山と渓谷社)。
ページいっぱいに拡大された花の写真は美しく、あまり見向きもされず、時には厄介者扱いされる雑草を見る目が変わりました。
ねじれた花穂に小さなピンクの花をつけるラン科のネジバナは、小さくてもやはりランの花。
ヤブジラミは「藪虱」と可愛げのない名前ながら、白く小さな花の集まりはレースのようにエレガント。
葉をもむとキュウリの匂いのするキュウリグサは、同じムラサキ科の忘れな草を小さくしたような水色の花でキュート。
その他、子どものころに茎相撲をして遊んだオオバコや、実を振って音を楽しんだナズナ、タネがはじけるのが楽しくて実を指でつまんだカタバミなど約100種が掲載され、ページをめくるたびに雑草と呼ばれる植物の姿に目を見張ります。
写真はキノコを撮らせたらピカイチの大作晃一さん。対象が植物となってもその腕がいかんなく発揮され、細部まで鮮明な写真は、花弁の形、雄蕊や雌蕊の様子、棘や毛の有無までルーペで観察しているかのようによくわかります。
文は多田多恵子さん。それぞれの花の特徴や見分け方、名前の由来などが簡潔で優しい文で解説されており、読むのも楽しい! ハコベの仲間の見分け方などとてもわかりやすいです。
さらに、この図鑑はレイアウトのセンスが抜群! 図鑑としてはもちろんのこと美しい花の写真集としてもお薦め。
春になってコンクリートの隙間や街路樹の植えますに雑草がたくさん。この図鑑を手に入れてから道端の雑草が気になって仕方がありません。
(R)