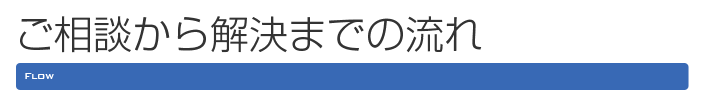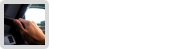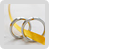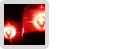ご相談から解決まではケースによって様々な流れがありますが、こちらでは当事務所の弁護士にご相談いただいた場合の各分野別に代表的な流れをご説明いたします。
交通事故解決
交通事故にあって、怪我をされた場合の流れを簡単にまとめます。
相手方(加害者側)に任意保険がついていることが前提です。
交通事故ケース(被害者)の流れ
- STEP01
- 怪我をしますと治療費が発生します。
治療費をどのように支払うかを相手方(加害者側)の任意保険と協議します。また、怪我の程度によっては、仕事ができない場合がありますので、そのときは休業損害について協議します。 - STEP02
- 怪我が治れば、慰謝料など損害賠償の総額を決めるために、相手方(加害者側)の任意保険と協議します。
後遺障害が残る場合は、後遺障害の等級の認定手続をします。
協議の結果、双方が合意すれば、示談書を作成し、損害賠償金が振り込まれます。 - STEP03
- 相手方(加害者側)の任意保険との協議がうまくいかない場合は、弁護士が被害者の代理人となることもあります。被害者の方の任意保険に、弁護士費用特約が付されていれば、弁護士費用を支払う負担がなくなりますので、弁護士に依頼される方が有利です。
- STEP04
- 弁護士が、相手方(加害者側)の任意保険と協議しても合意に達しない場合、法律上の手段としては次の三つが主なものです。
- 紛争処理センター
- 裁判所での調停
- 訴訟(裁判)
- STEP05
- 紛争処理センターは、訴訟までは望まず、比較的早く解決ができる紛争処理の方法です。
解決まで半年程度が目安です。当事務所でも積極的に活用しています。
もっとも、同センターで処理できる範囲には限界もあるので、そのときは訴訟を検討せざるをえません。 - STEP06
- 裁判所での調停は訴訟よりも簡易な手続きですが、紛争処理センターほど当事務所は活用しておりません。
- STEP07
- 訴訟(裁判)は、紛争処理センターや調停では打開できない場合にとられる手段です。
裁判所に申し立てをしますが、期間は争点にもよりますが、1年~2年程度はかかります。
離婚問題
離婚交渉(協議離婚)の流れ
離婚の交渉をこのようにしなければならないというものではありませんが、当事務所の弁護士をご依頼になる場合は、次のような流れで進めます(なお、交渉を希望されないことも可能で、その場合は離婚調停からになります)。
- STEP01
- 弁護士から、相手方に当方が代理人となり、交渉の窓口となったので、今後の連絡は弁護士宛に下さいという通知を書面でいたします(受任通知)。
- STEP02
- 受任通知が相手に届くと、交渉を開始します。
離婚に際して、決めるべきことは多いので(親権をどうするか、養育費をいくらとするか、慰謝料・財産分与をどのように決めるか、年金分割、面会交流をどうするか)、直接会って話すというよりも、郵便で当方の考えを伝え、細かいところは電話でという交渉方法が一般的です。 - STEP03
- 離婚をした場合に備えて、夫婦間で分かれていなかった家計などを整理していきます。
- STEP04
- 交渉がまとまれば、相手方との間で合意書を作成し、離婚届に記載をしてもらいます。公証役場で合意書を作成してもらう(公正証書)ことも場合によってはあります。
- STEP05
- 離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。
離婚調停の流れ
夫婦の話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。配偶者がDVをしているとき等話し合いが困難なケースは、話し合いをせずに離婚調停を申し立てることもあります。
調停をしないと離婚訴訟をすることができないのが原則ですが(調停前置主義)、相手が行方不明のとき、刑務所にいるときは調停を申し立てる必要はありません。
- STEP01
- 申立書を家庭裁判所に提出します。相手方の住所地の家裁で申し立てることが一般的です。夫婦間の合意で裁判所を定めることもできますが、なかなか合意できないことが多いです。
- STEP02
- 離婚調停を申し立てるときに、婚姻費用の調停や面会交流の調停を同時に申し立てておいた方がよい場合があります(この判断はご自身では難しいと思いますので、弁護士にご相談下さい)。
- STEP03
- 第1回の調停期日は申立てから1ヶ月程度後になることが多いです。
調停の運用の仕方は裁判所によって違いがあるかと思いますが、千葉家裁の場合、それぞれ30分ずつ調停委員が事情を聴くことを2回繰り返すので、合計2時間というのが一般的です。 - STEP04
- 離婚調停で、合意が全く成立しそうにない場合(一方は離婚を希望しているが、他方が強固に反対している場合)は、1回目や2回目で調停が終了する場合もありますが、合意できる見込みがあれば、調停期日が続きます。間隔は約1ヶ月~2ヶ月です。
- STEP05
- 合意が成立すれば、離婚となります。
裁判所が作成する調停調書を添付して、離婚届を出します。 - STEP06
- 合意が成立しない場合は調停は終了(不成立)となります。
離婚を求める場合は、離婚訴訟をするかどうか検討することとなります。
離婚訴訟の流れ
- STEP01
- 離婚訴訟は、訴状を作成して家庭裁判所に提出します。自分の住所地の家庭裁判所に提出することができます(ここが相手方の住所地に出さなければいけない調停とは異なるところです)。
- STEP02
- 第1回目の期日は、訴状を提出してから約1ヶ月後に設定されます。
- STEP03
- 第1回目の期日の前に、相手方から答弁書が提出されます。これには訴状に対する反論が書かれます。
- STEP04
- 答弁書に対して、更に再反論を書いていきます。この書面を準備書面といいます。
訴訟ではこのような書面の応酬が中心となります(口頭でのやりとりが多い調停とは様子が異なります)。
その為、1回の期日は約10分~30分で終わります。 - STEP05
- 訴訟になった場合でも約半分のケースは、双方の合意で終了します。これを「和解」といいます。
- STEP06
- 合意にならないケースは、判決となります。判決になる場合は必ず、夫婦を尋問することになります。このときの期日は1時間~2時間程度かかります。
- STEP07
- 家庭裁判所で判決となる場合は、1年~1年半程度かかります。和解となる場合は、それよりも早く終了します。
- STEP08
- 家庭裁判所で判決が出ても、一方が控訴すれば、訴訟は続きます。控訴があれば、高等裁判所に訴訟がかかります。高裁では、半年~1年程度かかります。
- STEP09
- 高裁で判決となった場合でも、さらに最高裁に上告することができるので、その場合では訴訟はまだ終わりません。このように判決を求める場合は、時間のかかる手続きとなります。
刑事事件
逮捕された場合の刑事事件の流れを説明します。
刑事事件の流れ
- STEP01
- 警察に逮捕された場合、被疑者ということになります。
被疑者はその翌日(又は翌々日)に検察官のもとに送致されます。
あまり重くない犯罪のときは、釈放されることもありますが、そうでない場合は検察官が勾留を請求し、被疑者は裁判官のもとに送られます。 - STEP02
- 裁判官が勾留を決定した場合、その日をいれて、10日間、身体を拘束されます(警察の留置場にいれられます)。
- STEP03
- 警察官、検察官が、その間、捜査をします。被疑者は取調べを受けることになります。
- STEP04
- 検察官は勾留10日までの間に、起訴するかどうかを決めることになっていますが、決められない場合は、更に10日間勾留期間を裁判官が決定することができます(つまり、起訴するまでに最大20日間勾留が可能です)。
- STEP05
- 検察官は、起訴するか、起訴しないか(不起訴)を決めます。
起訴は略式裁判(罰金)と正式裁判(罰金よりも重い)の二通りあります。
不起訴と略式は釈放されますが、正式裁判は引き続き、勾留されます。 - STEP06
- 起訴された後は、被疑者は「被告人」と呼ばれます。被告人になると、保釈請求ができます(起訴される以前は保釈ができません)。
- STEP07
- 正式裁判になると、法廷で期日が開かれます。
期日は起訴されてから、1ヶ月~2ヶ月後です(裁判員裁判は除きます。以下、同様) - STEP08
- 期日は事案に争点がなければ、1回で審理が終了、2回目に判決となりますが、争点が多い場合は、その程度に応じて、期日が複数日開かれます。
- STEP09
- 判決は、有罪の場合、執行猶予が付されるか、付されないか(実刑)です。
判決に不服があるときは、高等裁判所に不服申立て(控訴)ができます。