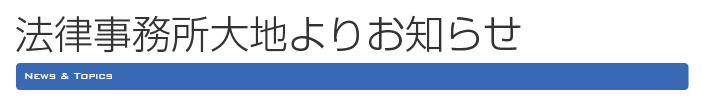【代表弁護士から】人生100年時代と隠居
2018年08月01日(水曜日)
人生100年時代などという言葉が聞かれるほど長寿の方が多い時代となってきました。
高齢化が進んでおりますが、一方で、組織や経済を活性化する必要もあって、このバランスを取るのは難しいですね。
会社などの組織では定期的に人事異動をして組織を活性化していくわけですが、小さな法律事務所だとそのような人事異動をするわけにもいきません。
そういえば、江戸時代には隠居という制度がありました。今年没後200年を迎える伊能忠敬も佐原の名主などを務めあげて50歳で隠居。51歳から江戸に出て、天文学や測量の道に本格的に入っていったのでした。
まだ元気なうちに後進に道を譲る隠居という発想は、現代でも見直されてよいかもしれません。
ところでさきほど隠居という制度が江戸時代にあったと書きましたが、隠居というのは明治以降現行憲法が施行される1947年までは、民法上に存在していました。
この隠居というのは、戸主が家督を他の者に譲ることをいいまして、家制度と結びついたものです。
隠居というものも家制度と深く関連づけられて理解されているようですが、家制度を離れれば年長者が有している利益や権利を手放して次世代に渡すという機能を有することは明らかです。
隠居というイメージは、隠居後に何もしない、のんびり暮らすというものですが、現代においては、伊能忠敬に範を取り、積極的に他の分野に打って出るということこそが求められるような気がします。
【スタッフ雑談】縄文展
2018年07月27日(金曜日)
東京国立博物館で開催中の「縄文-1万年の美の鼓動」展へ行ってきました。
有名な遮光器土偶や国宝の土偶、多様な文様と独特な形状の縄文土器、土製耳飾や貝輪などの装身具、動物やキノコを象った土製品など200点余りが「縄文の美」をテーマに展示されています。
土器や土偶のどれもこれも印象深かったのですが、最も心惹かれたのは火焔型土器。教科書で知ってはいるものの実物を目の前にすると、縄文の人々の思いが時空を超えて伝わってくるようで、力強い立体的な装飾と圧倒的な存在感に目が釘付け。芸術品のような土器で煮炊きをしていた縄文の人々の美意識や暮らしぶりをあれこれ想像しながら、しばし時を忘れて縄文の世界に浸りました。
7月31日からは縄文の国宝6点が全て勢ぞろい。
また、今週末と来週末は本館前広場でビアガーデン「トーハクBEER NIGHT!」も開催。縄文展とのコラボで、国宝の出土地域のクラフトビールも飲めるそうなので、今一度、縄文時代にタイムスリップしに行きたいと思っています。(R)
【代表弁護士から】弁護士の引退模様
2018年07月20日(金曜日)
事務所を経営している弁護士は自営業者なので定年というものがありません。
自分の進退は自ら決めるということになります。弁護士を辞める。事務所を閉める。つまり、「引退」は数ある人生の選択の中でも大きなものの一つといえるかもしれません。
私が弁護士になったころ(20年以上前)は、70歳代くらいになったら仕事は徐々に減らしていくけれども、弁護士登録は維持したままで、弁護士という名のもとにお亡くなりになるというのが一つの型でした。千葉県弁護士会では会員、即ち、弁護士登録をしている方はお亡くなりになると、FAXで全会員(千葉県内に事務所を有する弁護士)に訃報をお知らせすることとなっており、そのFAXが時々送られてきます。告別式には弁護士会の会長が弔辞を読むのが慣例となっているというようなことも聞いたことがあります。
このように弁護士は生涯現役というのが一つの型として存在していました。
最近は、いろいろと変わってきまして、この型というものがなくなりつつあります。
まず、若手弁護士が様々な事情から弁護士登録を取り消すということが見受けられます。弁護士登録を取り消すと、「弁護士」という名前で活動はできなくなりますが、「弁護士」としてではなく「法曹資格者」として活動ができればよいという割り切りもあるのでしょう。また、弁護士会費というものがかなり高いということもあり、弁護士登録の取消しに至るようです。若手でなくても、高齢となり、売上に比べて弁護士会費等の経費の負担感があるということになりますと、やはり、弁護士登録の取消しという選択となってくるようです。
弁護士の増加に伴う、弁護士の売上減少ということが、この辺に影響しているように思われます。
余裕のある状態で弁護士から引退する方もでてきています。60代や70代の方の中には、弁護士登録を取消したり、事務所を縮小して、半ば引退というような選択をされる方がおられます。
引退のタイミングというものはいろいろな要素を勘案して決めていかなければならず、難しい選択の一つだと思います。今まで経営してきた事務所を継承していくのか、それとも廃止していくのか、継承していくとすれば誰にどのように継承していくのかは、会社でいう事業承継と同じ問題が生じるように思います。
【スタッフ雑談】連休中に考えたことなど
2018年07月17日(火曜日)
猛暑が続いた海の日連休。さすがに野外でのテニス練習はからだが持たないので、活動はもっぱら涼しくなる夕方以降に変え、夜な夜な、というか、夜が明けるまでウィンブルドンとW杯をリアルタイムで視聴するという日々を過ごしていました。
ウィンブルドンは錦織選手が日本人選手としては松岡さん以来実に23年ぶりのベスト8進出、元世界№1のジョコビッチ選手が完全復活を遂げ優勝を果たし、W杯ではフランスが20年ぶりに世界制覇を成し遂げました。ウィンブルドンの男子シングルス決勝と、W杯の決勝は同日だったのでそれこそずっとテレビにはりついて、かじりついて見ていました。
被災地域のことを考えると、こうやって普通に暮らし、涼しい部屋でテレビを見ていることに、それぞれの「今」がこんなにも違うことに愕然として罪悪感にさいなまれたりするのですが、自分にできることは限られているし、自分にできる範囲で(募金することくらいしか思いつきませんが)、自分のできる協力をずっとしていこうと思いました。(S)
【代表弁護士から】没後200年の伊能忠敬
2018年07月05日(木曜日)
7月になりました。7月というと中旬ころまで梅雨というのが普通なのですが、今年は6月中に早々と梅雨が明けてしまい、6月下旬から猛暑。長い夏となりそうです。
今年で没後200年の伊能忠敬。50歳過ぎてから江戸に出て、その後、全国を測量して回るという後半生を送ったことから、スーパーマンのような人であるとみられていますが、実際はどんな人だったんだろうと思い、川村優著「新しい伊能忠敬」を読んでみました。
川村は伊能忠敬がその娘に送った手紙から、忠敬には喘息があり、足腰が弱く、胃腸が弱くて胃腸障害に苦しみ、痔持ちで、69歳のときには自らの歯をほとんど失った状態であったと結論づけています。「忠敬の人生はごく常人のごとく山あり谷ありで、栄光よりもむしろ苦難の連続であった。加えて、はかり知れない病弱との戦いが常日頃彼を苦しめていたのである」(同書)にも関わらず、自らの課題に立ち向かい、夢を実現しようとしたところに、人は惹かれるのでしょう。
忠敬が佐原から江戸に出た歳(51歳)と同い年である自分には何がこの後できるのか、己の胸に問う日々です。