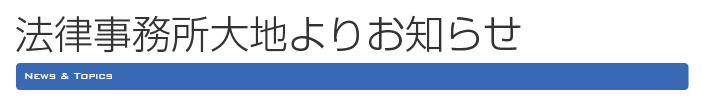【代表弁護士から】法律実務に携わっていて今、思うこと
2018年09月07日(金曜日)
法学部に入った時に、「六法全書って全部覚えるものなの?」とか「法律を知っていれば全て物事が解決できるの?」というようなことを周りの友人に聞かれたことがあります。
そのときにどう答えたのか全く覚えていませんが、今ならこう答えます。
「六法全書って全部覚えるものなの?」⇒全くそんなことはありません。
「法律を知っていれば全て物事が解決できるの?」⇒法律を知っていたからって全て物事が解決できるわけではありません。
法律を知らない方からすると、法律というのは網の目のように張り巡らされていて全然スキがないものと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
この世の全ての出来事に法律の規制をすることなんて不可能ですし、世の中の動きが早ければ一度作った法律も古びてしまいます。
結局、物事を解決するのはヒトの力だな、法律は解決の指針というか、解決のヒントになるだけで、それが物事を解決することにはならないなと思います。
最近はとかくどこも余裕がありません。
余裕がなくなって人情がなくなった、そんな気がします。
そうなると法律で決まったことだけやろう、法律に触れてないことだからやってもいいだろうというような発想になり、ますますギスギスしてきます。
20年以上前と比べると、そういう傾向が強まったような気がします。
しかも、それがあんまり意識されていなくて、人情がなくなっていくのが当然のように考えられている今の世の中の風潮が気になるところです。
【スタッフ雑談】再び縄文展
2018年08月27日(月曜日)
思っていた以上に可愛らしい! 国宝土偶の「縄文のビーナス」と「仮面の女神」。
先月は展示期間前で見ることができなかったので、再度、東京国立博物館の縄文展へ行ってきました。
テレビや雑誌でも取り上げられ、夏休み期間中ともあって、前回訪れた時より館内は来館者で賑わっていましたが、展示はそれほどストレスなく見ることができ、お気に入りの火焔型土器を思う存分鑑賞後、縄文の国宝が展示されている部屋へ。
部屋の奥に展示されているお目当てのビーナスと女神にいそいそと近づき、正面、後ろ姿、真横とゆっくり拝見。
「仮面の女神」は思っていたよりも大きく、美しいフォルムと堂々とした感じがまさに「仮面の女神」。胴に施された紋様や紐で縛って仮面を付けている様子など全体的に作りが丁寧。
「縄文のビーナス」は吊り上った目と大きなお尻が印象的。特に後姿が何とも言えずキュート。表面は磨かれ、粘土の中の雲母が照明にあたってキラキラ。
写真で見るより可愛らしい土偶を前に、縄文時代へと想いを巡らし楽しいひと時を過ごしました。
この二つの国宝土偶は、茅野市尖石縄文考古館に普段は展示されているそうで、ここは「ぐるぐる博物館」(三浦しをん著)という本を読んでから行ってみたいと思っている博物館の一つ。
考古館は「縄文のビーナス」が発掘された尖石遺跡の史跡公園内にあって、土偶の出土状況や八ヶ岳山麓に栄えた縄文文化について展示されているそうなので、八ヶ岳方面へ行った時に寄ってみたいと思っています。(R)
【代表弁護士から】残暑お見舞い申し上げます
2018年08月17日(金曜日)
今年の夏は猛暑といわれており、観測史上最高記録が塗り替えられてしまうほどでした。
関東では6月に梅雨があけてしまったので、長い夏となりました。
ただ、さしもの猛暑も8月となると徐々に衰えてきたような気もします。
風の中にも少~しずつですが、秋の気配が漂ってきたような気もしないではありません。
千葉県は東京に比べれば比較的温暖な気候で、千葉市ですと東京の都心と比べて1度~2度は違うのではないかと思います。
以前東京に住んでいたときは、都会のコンクリートジャングルの中、風も通らず、耐え難い思いをしました。
千葉に住んでいますと、そこまでではないのですが、ただここ最近の暑さには千葉にいてもかなりこたえます。
快適な夏を過ごすには、もっと北の東北地方よりも北に住むほかないのではないかと思ったりもしますが、ただ冬は冬で厳しい寒さのようでもあるでしょうし、なかなかどこに住むのが良いのかというのは難しい問題がありますね。
【スタッフ雑談】連日の猛暑で
2018年08月15日(水曜日)
個人的に夏は好きな季節なので、毎年の夏が楽しみでしたが、いささか今年の異常なまでの猛暑には体もこたえますね。趣味のテニスも練習はもっぱら夕方4時以降から夜まで、ナイターでの練習が中心となっています。
あまりにも晴天が続いているせいか、我が家の方では8月初旬で既に稲刈りが始まっていたりします。おそらくこのお盆休み期間中に多くの農家が稲刈りをはじめるのではないかなぁと。今年は新米をいただくのも早まりそうです。(S)
【お知らせ】無料電話相談は8月10日までとなります
2018年08月03日(金曜日)
ご好評いただいておりました無料電話相談ですが、本年8月10日受付分をもちまして終了させていただきます。
8月11日以降は相談費用などは次のとおりとなります。
初回相談=面談での相談に限り無料です(初回の電話相談は行いません)。
再相談=有料となり、相談費用に変更はありません(再相談は面談だけでなく、電話での相談も対応可能です)。