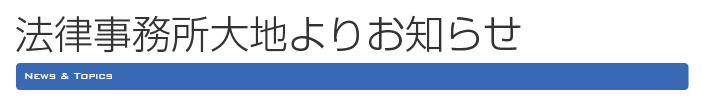【スタッフ雑談】夏旅行してきました
2017年07月19日(水曜日)
先日、早めの夏休みをいただき、中国地方へ旅行してきました。
羽田から岡山へ飛び、倉敷に立ち寄り、玉造温泉で宿泊。
出雲大社、足立美術館、鳥取砂丘をまわって、神鍋高原で宿泊。
念願だった天空の城(日本のマチュピチュ)などと呼ばれている竹田城跡を見学し、天橋立を眺め、伊丹から羽田へ戻るという盛り沢山な3日間でした。
かなり長距離移動ですが、これも旅行会社のツアーだからこそなせる業ですね。以前は自分で色々計画して個人旅行をしていましたが、最近はこのような旅行会社のパックツアーを利用することが増えました。経済的な面と時間的な面を考えるとツアーはお得ですし、何しろ自分であれこれ考えなくても連れて行ってもらえるのも有り難く、だんだんそちらにシフトしてきました。(移動はバスで効率よく、車内でビールを飲みながら昼寝、見学も時間を区切ってだらだら無駄に疲れない、楽でいいです。おかげでめっきりツアー派です。)
今回は初めて行くところばかりだったのでとても有意義でした。特に竹田城跡は、雲海がなくても、山城特有のあの眺望と雄大さには本当に感動しました。見学通路で順路が決められたり、人数制限もされますが、ぜひ一度は訪れて欲しい所です。お勧めです。(S)
【代表弁護士から】紛争を解決するためには裁判所を利用しなければならないときもあります
2017年07月11日(火曜日)
普通に生活している方にとっては、裁判など関わりになりたくないもの、できれば裁判所などは一生行きたくないものとお考えのことと思います。
つまり、裁判の世界というものは、日常との言葉の対比でいえば非日常。正常という言葉の対比でいえば、異常なものという風にみられてしまっています。
しかしながら、人生とは因果なもので、一定割合で紛争というものは発生してしまうものであり、また、その紛争を解決するためには裁判所を利用することが必要になる場合もあります。
弁護士という職業は、そのような裁判所、裁判、調停などを利用する方々の道案内役なのですが、非日常・異常な世界にどっぷりと浸かってしまっていますと、自ずと普通の方々とは違う感覚になってしまうのは否めません。
弁護士の悪いところは、「裁判などするのは大したことではないですよ」とか、「気軽に裁判所を利用しましょう」などと思っているところです。
弁護士としては裁判所に行くのは当たり前。毎日のように行っていますから、日常的、職業的行為になるのですが、一般人にはそう思えませんので「裁判などは大したことではない」などと考えるのは間違いです。
私の考えを申し上げておきますと、生きている限り、紛争というものは多かれ少なかれ起きてしまいます。そのような紛争があっても話し合いで解決するのが一番です。
しかし、人々の間の信頼関係が希薄になり、また、自分の考えに固執する人々が増えてきているような現代にあっては、話し合いをしてもポイントのずれたものになったり、お互いの言いたいことだけを言ったりとなり、話し合いがちっとも紛争解決にならないということが起こります。そういう場合に紛争を解決するためにやむを得ず、裁判所という機関を利用するのです。裁判というと、どうも「判決」というイメージが強いのですが、民事裁判の大半は「和解」という名前の合意で終了するものであり、一刀両断の判決というのは案外少ないのです。裁判官も「判決」よりは「和解」」を好みます。
つまり、裁判所を利用するといっても、話し合いのプロセスの1つのバリエーションなのです。
もちろん、裁判所を利用しないということもできるのですが、その場合は、交渉が進展せず、泣き寝入りということになりかねません。
そうはいってもやはり裁判は嫌だという方は多いですし、それはそれで仕方のないことだとは思います。ただ、これまでの多くの依頼者に会ってきて感じるのは、裁判をするまでにはかなりためらっていた方が、裁判の遂行の過程では熱心になることです。江戸時代も裁判というものは相当数あったようですし、案外、日本人は裁判嫌いとは言えないのかもと思っています。
【代表弁護士から】不動産の事件が減りましたね
2017年06月29日(木曜日)
私が弁護士としてのキャリアを始めたのは1995年なので、もう20年以上前のことです。事務所の案件としてあったからかもしれませんが、不動産が絡む訴訟というのが結構ありました。今は、そこまで多くありません。
裁判所では本日開廷される事件の一覧を見ることができますが、そのリストを眺めていても不動産の事件は多くはないので、減ったのは事実なのでしょう。不動産のことは以前に比べれば争いの種になりにくくなったといえるでしょう。
不動産に執着しなくなったともいえます。1995年当時は境界争いは珍しくありませんでした。境界争いをしている不動産の面積はそれほど大きくないので、弁護士費用のほうがこの不動産の面積よりも高く付くのでは・・・と思っていました。
不動産への執着が減ったということの現れが、空き家問題なのだと思います。年老いた親が借地に家を建てて住んでいるのだけれど、亡くなった後は誰も使わないから、どうやって借地権を返上したらよいのだというご質問もいただきます。
借地に建つ建物を利用するという意欲がなくなっています。管理するコストとかが面倒だから、それなら借地を返上して、底地権者に返して、底地権者の方で建物を処分してほしいという考えの方が勝つ時代です。
不動産の事件が減ってますから、若手弁護士は不動産の実務はあまり知りません。というより、そういう実務に触れ合う機会がない。不動産の事件よりも、家事事件、不貞の損害賠償請求訴訟というのが多くなれば、そうなるのもやむを得ません。
「時代」といってしまえば、それまでですが、10年、20年で随分変わるものだなと思います。今後10年でまた更に何かが変わるでしょう。変化についていける弁護士でありたいと願って日々精進です。
【スタッフ雑談】湖北から古利根沼へ
2017年06月23日(金曜日)
日秀観音、将門神社、将門の井戸、相馬郡衙正倉跡、足尾山神社、伊勢山天照神社などの神社仏閣や遺跡を巡るというもので、今回は火山好きな人と、歴史好きな人たちとの合同の散策会。
興味、関心が異なる人たちと一緒に散策をしてみたところ、庚申塔や板碑を見ても、火山好きな人たちはこれは凝灰岩、こちらは安山岩などと材質に関心があり、一方、歴史好きな人たちは彫られている仏像や神像、梵字などを興味深く観察しており、様々な角度から話しが飛び交う会となりました。
歴史や地質的な話しを聞くのはもちろん楽しかったのですが、庚申塔や板碑に目を輝かせ嬉しそうに話しをする人や、石塀や石塔などの材質について語り出すと止まらない人たちの幸せそうな顔をみていると、こちらまで笑顔に。
歩行距離は2万歩にも及んだので足は痛くなりましたが、散策後に皆で飲んだビールはことのほか美味しく、疲れもどこかへ吹き飛ぶ楽しい一日となりました。
我孫子周辺を散策したのは初めてでしたが、時間が足りず芝原城跡など予定していた場所を全て回りきれなかったので、また散策に行ってみようと思っています。
(R)
【代表弁護士から】「わたしたちの茂原」と茂原市史
2017年06月16日(金曜日)
私は茂原市の出身で高校まで茂原市に住んでいました。
自分たちの住んでいる地域の地理とか歴史というのは、小学校の3年生とか4年生のときにまずは学ぶものですよね。
小学校3年生のときに、茂原市のこと、4年生で千葉県のことを勉強したように記憶しています。
副読本があり、茂原市のは「わたしたちの茂原」というものでした。
確か、この本は貸与だったような記憶です。
つまり、その年は貸してもらえるけれども、次の年になったら下の学年の子のために返さなければならないものでした。
こんなことを考えていたら懐かしくなったので、図書館で今の副読本を借りてみました。
初版が昭和41年。
50年以上前からこのようなテキストをもとにして、郷土のことを教えていたんですね。
表紙が児童が描いた七夕祭りの絵。やはり茂原市といえば七夕祭り。昔に比べるとJRさんも力を入れているので、茂原市以外の方も来るようになったのかもしれません。
昔の写真も豊富にあり、茂原というのは歴史を大事にしているところなのかと改めて感じました。
市の歴史といえば、市史というものがどこの市でもあるものなので、茂原市はどうなんだろうと思って調べてみました。
茂原市史が出版されたのは1966(昭和41)年で、副読本の初版と同じ時期です。
残念ながらそれ以後は茂原市史は改訂されておらず、この1966年版が茂原の歴史の決定版ということになっています。
随分前のものしかないんだなぁと思っておりましたら、どうも茂原市では市制施行70周年(2022年)を目指して、新たな茂原市史の編さん作業を進めているようです。
茂原市史の編さん事業は茂原市教育委員会の主導で行われており、茂原市史編さん委員会条例をが2017年3月21日に市議会で可決され、4月1日から施行されています。
茂原市史編さん委員会が組織され、今後執筆が進められていくものと思われます。
5年後には新しい茂原市史を手にとることができるようです。