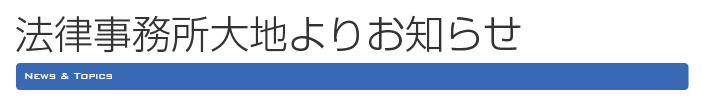【代表弁護士から】弁護士の懲戒処分(業務停止)を考える
2017年11月06日(月曜日)
2017年10月11日付で東京弁護士会は、弁護士法人アディーレに対し業務停止2ヶ月の懲戒処分を行いました。
アディーレはかなりの数の案件を扱っていたため、アディーレの依頼者の方を初めかなりの混乱となりました。
東京弁護士会はアディーレ専用の電話回線をもうけましたが、かなりの件数が殺到したため「繋がらない」との批判を当初は受け、それが報道されるという事態となっております。
また、ネット上を見ると、東京弁護士会のした業務停止処分自体にも批判が巻き起こっています。
今回は、弁護士への懲戒処分等について考えてみたいと思います。
【懲戒処分の種類は?】
懲戒処分の種類としては、軽い順から
ア 戒告
イ 業務停止(2年以内)
ウ 退会命令
エ 除名
があります。
これは「弁護士法」という法律に記載されておりますが、その内容がどのようなものかについての定義規定のようなものは法律には規定されていません。
それゆえ、法律をどのように解釈するかに任されています。
弁護士会が「業務停止」をどのように解釈しているかについては、日弁連の理事会の決議というレベルで次のように決まっています。
【業務停止処分とはどのような処分?】
① 依頼者との委任契約を直ちに解除しなければならない(業務停止期間が1ヶ月を超える場合)
② 顧問契約も直ちに解除しなければならない。
③ 裁判所にかかっている事件について直ちに辞任しなければならない(業務停止期間が1ヶ月を超える場合)
④ 懲戒された弁護士は依頼者等に事務の引き継ぎをしなければならない
⑤ 法律事務所の表示は除去しなければならない(ホームページも見ることができなくなります)
今回のアディーレの業務停止処分に次のような声がありました。
”弁護士会は指導ができなかったのか。指導もせず、いきなり業務停止処分はおかしいのではないか。”
Aの声の「弁護士会は指導ができなかったのか」ですが、行政指導のような指導というのは弁護士会はしませんね。業界にいると、そのような指導を弁護士会がしないのが当たり前なので、「弁護士会は指導ができなかったのか」と尋ねられても、”そのようなことはしていません”としか答えられないだろうなと思ったのですが、今回のことを機になぜそのような指導をしないのか考えてみました。
形式的には、「弁護士会が弁護士を指導するというような規定がない」からなんでしょうね。ただ、行政だって行政指導というのを規定に基いてやっていたわけではないので(今は行政手続法がありますが、その制定前は規定がありませんでした)、規定がないというのを理由に指導しないというのは理由になっていないともいえます。
それに弁護士という人種の中には、そのような法律の根拠がないことをされると、「一体それはどのような根拠に基づいて行っているのか。根拠が無いのであれば、そのような行為は違法ではないのか。それに従わなければならないのか。従ったことによって損害を被ったら損害賠償してくれるのか。」などと言い立てる方もいらっしゃいますので、おいそれと「指導」などというものができないのかもしれません。
今回のアディーレの処分の対象となった行為は、過去の行為であり、弁護士会が懲戒処分をするだいぶ前に処分対象とされるような行為は終わっていますので、指導そのものができなかったかもしれません。
ただ、今回の業務停止処分に対して発せられた皆さんの疑問はもっともなところもあり、処分をした弁護士会は丁寧な説明を心がけなければならなかったと思いますが、残念ながらそのような情報発信は行われませんでした。
懲戒処分は懲戒委員会という弁護士会の中でも独立の委員会が議決するとはいえ(それゆえ会長すらこの議決に対してどうこう言えません)、決まった処分については弁護士会として説明をしなければらない立場にあるのに、ほとんど公式的な情報を発信しなかったのは、東京弁護士会の危機管理が疎かであったとしか言いようがありません。
今回のことで弁護士会は無様な姿をさらしたといえ、信頼回復は容易ではないような気がします。