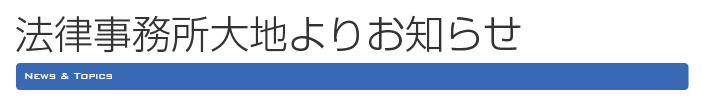【代表弁護士から】最高裁への上告、上告受理(民事・家事訴訟)
2016年09月29日(木曜日)
裁判手続(訴訟手続)は、法律テクニックが必要ですが、最高裁への上告申立て等については高度なものが求められます。
最高裁への申立ては、上告申立てと上告受理申立てに分かれます。それぞれ理由が違うので、ここで間違ってはいけません。
上告申立てには「上告理由」が必要です。
上告理由のメインは、憲法違反ということです。
条文では「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる」(民訴法312条1項)と規定されています。
上告受理申立てというのは、上告理由がなくてもできますが、「判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」でなければなりません(民訴法318条)。
上告申立てと上告受理申立ては、別個の手続きで申立て段階で明確に区別されているので、正しく振り分ける必要があります。
憲法違反の事件というのは、そう多いものではないので、上告受理申立ての方が申立てしやすいのは確かです。もっとも、上告受理申立ての場合、最高裁が事件を受理するか受理しないかは最高裁の自由ということになっているので、その点が上告申立ては違う厳しいところです。
いずれにせよ「事実認定」の問題は最高裁では基本的に扱いません。
最高裁が「法律審」と言われ、法律問題しか扱わないからです。最高裁には15人しか裁判官がおらず、事実の問題を扱うにはマンパワーが不足しています。
条文上はこんな風に書かれています。「原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する」(民訴法321条)。
「事実」については高裁までにしっかり争っておかないといけません。